
入社2年で人気タイトルのプロデューサーに。
長期運営に必要な「思考」と「視点」を探る
3社のモバイルゲーム開発現場でキャリアを重ねたのち、2020年DeNA Games Tokyo(以下、DGT)へ入社。入社後は開発プランナーとして『FINAL FANTASY Record Keeper(以下、FFRK)』にアサイン、以降一貫して同タイトルに従事。開発と運営の両方で重要な役割を果たし、さまざまなポジションを経ながらチームをリード。入社2年でプロデューサーにスピード就任。
鈴木 貴之
企画部・プロデューサー
2020年中途入社
※当記事は2024年のインタビュー内容となります
Q1.『FFRK』におけるプランナー、ディレクター、プロデューサーの役割の違いについて教えてください。
まずプランナーですが、他職種と連携した上で企画に関する様々なアウトプットと、その進行管理がメイン業務となります。アウトプットを具体的に説明すると、ボスキャラならボスのギミックを作ったり難易度調整をしたり、ガチャだったらキャラクターの性能をチューンナップしたり。そういった部分の設計までを行うポジションです。
『FFRK』にはバトルチームと運営開発チームという複数のチームがあり、それぞれのチームごとにディレクターを配置しています。各領域のコンテンツや運営開発の責任者として、お客さまに喜んでいただけるか、クオリティが求められるレベルに達しているか、などを担保するのがディレクターです。
プロデューサーに関しては、『FFRK』と他のタイトルとで少し違いがあります。予算やスケジュール、人員の管理、社内外との窓口業務など、経営視点でのチーム運営がDGTにおける通常のプロデューサー業務です。『FFRK』ではそれに加え、長期的な観点でのメンバーの育成促進やコンテンツ全体の責任者も兼ねています。プロデューサーというより、マネージャーや総合ディレクターに近い業務も行うイメージです。
『FFRK』にはバトルチームと運営開発チームという複数のチームがあり、それぞれのチームごとにディレクターを配置しています。各領域のコンテンツや運営開発の責任者として、お客さまに喜んでいただけるか、クオリティが求められるレベルに達しているか、などを担保するのがディレクターです。
プロデューサーに関しては、『FFRK』と他のタイトルとで少し違いがあります。予算やスケジュール、人員の管理、社内外との窓口業務など、経営視点でのチーム運営がDGTにおける通常のプロデューサー業務です。『FFRK』ではそれに加え、長期的な観点でのメンバーの育成促進やコンテンツ全体の責任者も兼ねています。プロデューサーというより、マネージャーや総合ディレクターに近い業務も行うイメージです。
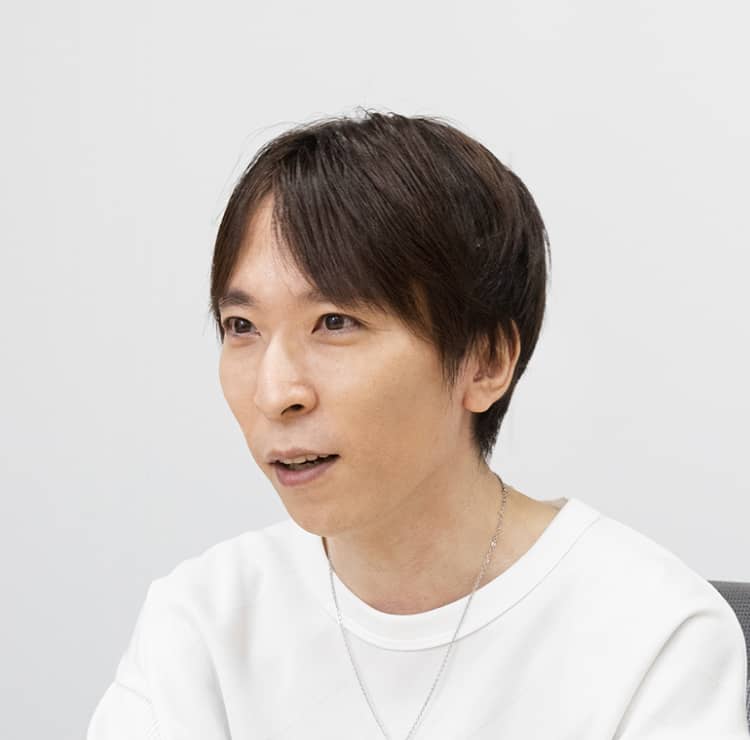
Q2. 最初にDGTの開発環境に触れたとき、どのような感想を持ちましたか。
個々の実装力が高いのを感じました。それはプランナーに限らず、エンジニアもクリエイティブ職もですね。
あとは柔軟性が高く、チャレンジを恐れない人が多いことにも感心しました。現場の声が反映される環境が整っていますし、提案しやすい空気も醸成されているので、チャレンジングなことに取り組みやすいのだなあ、と。この雰囲気は今ももちろんありますし、ずっと続いてほしいカルチャーです。
あとは柔軟性が高く、チャレンジを恐れない人が多いことにも感心しました。現場の声が反映される環境が整っていますし、提案しやすい空気も醸成されているので、チャレンジングなことに取り組みやすいのだなあ、と。この雰囲気は今ももちろんありますし、ずっと続いてほしいカルチャーです。
Q3. 入社後2年でプロデューサーに就任しました。どんな道のりを歩んできたのでしょうか。
前職ではリードプランナー、運営や開発のディレクター職などを経験していたので、その経験を買われての入社だったと思います。
DGTでの最初のポジションは、開発プランナーです。その後、開発リードプランナー、開発ディレクター、運営開発ディレクターを経て、プロデューサーに就任しました。実は入社前に「ディレクターを任せたい」とは言われていたので、最初のアサインの時はそこを見越してリードプランナーやディレクターの視点を意識しつつ、タイトル内の諸々のキャッチアップに努めていた、という感じです。
ディレクター時代はプロデューサーと一緒に上位部分に関わる意思決定をやっていたのもあって、タイトル全体の今後の方向性を考えていましたし、自ずとプロデューサーに近い視点を持てるようになりました。
また、プライベートでも徹底的にゲームをやり込み、ユーザー側と運営側の両者のスタンスをバランス良く考慮するよう心掛けました。2年でのプロデューサー就任は早い方だと言われますが、こういった姿勢を評価されたのかな、と捉えています。
DGTでの最初のポジションは、開発プランナーです。その後、開発リードプランナー、開発ディレクター、運営開発ディレクターを経て、プロデューサーに就任しました。実は入社前に「ディレクターを任せたい」とは言われていたので、最初のアサインの時はそこを見越してリードプランナーやディレクターの視点を意識しつつ、タイトル内の諸々のキャッチアップに努めていた、という感じです。
ディレクター時代はプロデューサーと一緒に上位部分に関わる意思決定をやっていたのもあって、タイトル全体の今後の方向性を考えていましたし、自ずとプロデューサーに近い視点を持てるようになりました。
また、プライベートでも徹底的にゲームをやり込み、ユーザー側と運営側の両者のスタンスをバランス良く考慮するよう心掛けました。2年でのプロデューサー就任は早い方だと言われますが、こういった姿勢を評価されたのかな、と捉えています。
Q4. DGTでのキャリアを通じて成長できたこと、また、今後の課題について教えてください。
特にプロデューサー就任後は、自分のスキルセットを広げることができたように思います。まずは開発と運営の現場が緊密に連携できる体制を整え、チームが目指す方向性を明確にしました。さらに現場でさまざまな実装に対応できるよう体制を整え、それまで属人化しがちだった業務などをマニュアル化したことで、突発的な事象にも対応しやすくしました。それまであまり経験のなかったマネジメント領域については、大きな成長機会に恵まれたと感じています。
一方、プロジェクトの持続可能性をいかに高めるかが今の課題ですね。特に『FFRK』のような長期運営タイトルでは、新しいユーザーを引き込みつつ、既存ユーザーを飽きさせないコンテンツを提供することが重要なんです。どうすればチーム全体の創造力を引き出し、常に新しいアイデアを取り入れられるか…。難しいけれど必ずクリアしたいミッションです。
一方、プロジェクトの持続可能性をいかに高めるかが今の課題ですね。特に『FFRK』のような長期運営タイトルでは、新しいユーザーを引き込みつつ、既存ユーザーを飽きさせないコンテンツを提供することが重要なんです。どうすればチーム全体の創造力を引き出し、常に新しいアイデアを取り入れられるか…。難しいけれど必ずクリアしたいミッションです。
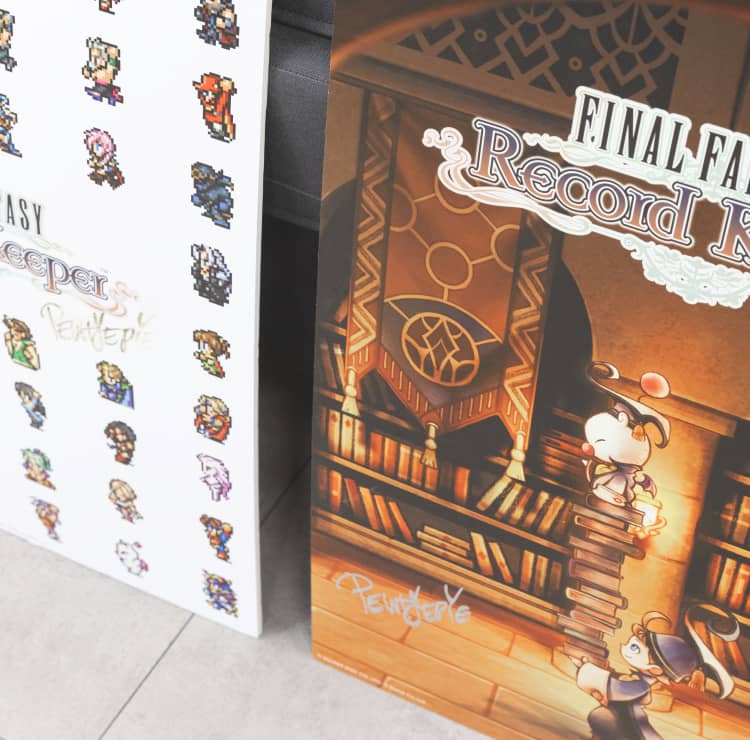
Q5. タイトルに貢献できたと感じていることはありますか。。
『FFRK』は長きにわたって愛されてきたタイトルです。プレイしてくださるお客さまにとって何が一番大切なのか。それはやっぱりこの先もお楽しみいただけるよう、長く続けていくことだと思うんです。それゆえ、入社以来、一貫してユーザー視点を第一に考えてきました。そんなユーザー視点を持ちつつ、ゲームプレイにおいてお客さまが何を求めて楽しんでいるのか、プレイサイクルから徹底的に検証し、常に見直すことを心がけています。
ただ、タイトルが長くなればなるほどマンネリ化もするので、今はマーケティングにも力を入れ、ゲーム内にとどまらずゲーム外でも新しい体験を提供できないか試みています。
また、お客さまからのご意見にはできる限り対応するようにしています。おかげさまで、いくつかの施策で嬉しい反応をいただきました。これは決して自分の力だけでは成し遂げることはできません。ただ、チーム全体にこの思想を浸透させられたのは、1つ貢献できたことかなと思います。
ただ、タイトルが長くなればなるほどマンネリ化もするので、今はマーケティングにも力を入れ、ゲーム内にとどまらずゲーム外でも新しい体験を提供できないか試みています。
また、お客さまからのご意見にはできる限り対応するようにしています。おかげさまで、いくつかの施策で嬉しい反応をいただきました。これは決して自分の力だけでは成し遂げることはできません。ただ、チーム全体にこの思想を浸透させられたのは、1つ貢献できたことかなと思います。
Q6. DGTのプロデューサーには、どのような資質が求められていると考えますか。
コンテンツ制作にあたり、お客さまをしっかりと見ながら数字も手堅く残す、という2つのことをバランスよく実行できるプロデューサーが求められていると考えています。利益だけ、お客さまのUXだけ、ではダメ。バランス感が重要だし、それができている人はちゃんと結果を出していますね。
Q7. 今後の目標について教えてください。
まずは『FFRK』を長く続けること。10年続いたのもすごいことですが、10周年はあくまで通過点としてもっと先まで続けられると嬉しいです。実は今まで、社内の他のタイトルに目移りしたことがないんです(笑)。自分がこのタイトルに関わっている間は責任を持ってやり遂げたい、という思いが強いので。
あとは、最近マーケティングに取り組み始めたように、業務範囲を特定の領域に閉じず、できることを増やしたいと考えています。プロデューサーとしてのスキルをさらに高め、常に成長し続ける人間でありたいです。
あとは、最近マーケティングに取り組み始めたように、業務範囲を特定の領域に閉じず、できることを増やしたいと考えています。プロデューサーとしてのスキルをさらに高め、常に成長し続ける人間でありたいです。







